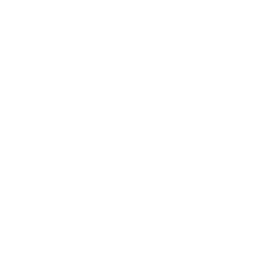研究院長挨拶

大学院農学研究院長
大学院生物資源環境科学府長
農学部長
(資源生物科学部門 教授)
日下部 宜宏
九州大学農学系教育・研究組織は、教員が所属する研究組織 「大学院農学研究院」、大学院教育組織の「大学院生物資源環境科学府」、そして学部教育組織の「農学部」から構成されています。
九州大学農学部は、生物生産、生物機能、生物環境などの関連分野において、国際的に通用する専門知識はもちろん、課題解決能力やバランス感覚を備えた多様な人材を育成しています。これを実現するために、生物資源環境学科のもと、4コース11分野からなる教育体制を採用しています。これらの11分野の学術基盤は、生物学、化学、数物科学、社会科学など多岐にわたり、学生に幅広い視点から総合的な教育を提供しています。
入学試験は、前期日程に加えて、小論文による総合的な評価を行う後期日程試験や、小論文と面接を組み合わせた総合型選抜を実施し、さまざまな視点から優れた人材を選抜しています。入学に際しては、学部一括入学制度を採用しており、専門性が高くなるコース・分野の選択は、農学全般を俯瞰できるようになる2年後期に行われます。この間、自己の適性を多くの判断材料のもとでじっくり考えられるようなカリキュラムを整えています。近年では、デジタルトランスフォーメーション(DX)教育にも重点を置き、農林水産・食品・生物関連産業のDX化を担う人材の育成を進めています。また、英語による授業などを通じて学位を取得可能な「農学部国際コース」を開設し、外国人留学生と日本人学生の双方を受け入れています。この国際コースは、全国的にも先駆的な理系の双方向ダブルディグリー・プログラムを、アメリカ・北アリゾナ大学やタイ・カセサート大学と連携して開始しています。さらに、留学を通じた価値創造人材の育成事業やインターネットを活用した海外大学との共同授業(COIL型教育)を積極的に推進し、国際的視野を持つリーダー人材の育成に力を入れています。
九州大学大学院生物資源環境科学府は、資源生物学、環境農学、農業資源経済学、生命機能科学の4専攻の下に、9教育コースを設置しています。修士課程では、専門知識を深めるだけでなく、課題探求・解決能力や戦略的企画能力を備えた研究者の育成を目指すとともに、バランス感覚に優れ、柔軟な思考力を持つ高度な専門職業人の養成にも注力しています。博士後期課程では、専門性と国際性をさらに高め、豊かな人間性と創造性を持つ優れた研究者を育成することを目指しています。また、次世代の生物資源環境科学を切り拓き、指導的役割を果たす大学教員などの教育従事者を養成しています。さらに、社会人入学の推進や優秀な留学生の受け入れにも積極的に取り組んでおり、完全英語で学位を取得できる「国際コース」を開設するなど、国際的な学びの場を提供している点も本学府の大きな特徴です。
九州大学大学院農学研究院には、資源生物科学、環境農学、農業資源経済学、生命機能科学の4部門が設置され、部門の下に複数の研究分野を含む講座を配置しています。「生命、水、土、森、そして地球から学び得た英知を結集し、人類の財産として次世代へ伝え、人類と地球環境の豊かな共存を目指して、進化する農学を実現する」というミッションのもと、生物資源や環境に関する教育・研究、国際協力、社会連携を通じて、食料や生活資材の安定供給、生物多様性の保全、そして人類の健康と福祉に貢献しています。これを実現するため、4つの主要な研究領域を中心に、革新的な研究と教育活動が展開されています。
- 新農学生命科学領域:生命科学の急速な発展を背景に、生物機能の解明・利用・創成を目指しています。
- 環境科学領域:地球規模での環境保全の立場から、生物多様性に配慮した環境調和型・物質循環型の持続的な生物生産・農村空間システムの構築を推進しています。
- 国際アグリフードシステム領域:アジアモンスーン地域における潜在的食料生産力に着目し、生物資源、生物利用、環境保全、農村開発を含む国際的な食料システムの構築を目指しています。
- 食科学領域:食の安全・安心に対する社会的ニーズを踏まえ、食料の機能性・安全性や、信頼できる食料供給システムの構築を推進しています。
九州大学は、Vision 2030において「総合知で社会変革を牽引する大学」を目指し、脱炭素、医療・健康、環境・食料の3つの重点領域を掲げています。多様な学問分野を包含する農学研究院は、これらの領域における社会課題解決において中心的な役割を担うことが期待されています。特に、地球規模での食料問題と環境問題に取り組む中で、生物多様性の保護や環境保全、持続可能で安心・安全な食料供給、そして人類の健康と福祉の向上を目指し、教育・研究・社会貢献の各分野で革新的な挑戦が続けられています。これらの活動を通じて、地域社会のみならず、グローバルな視点で持続可能な社会の実現に向けた先駆的な役割を果たし続けています。
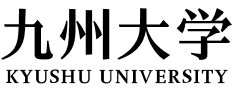

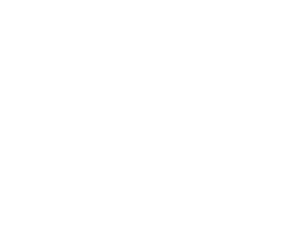
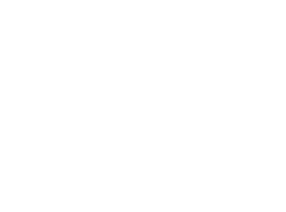
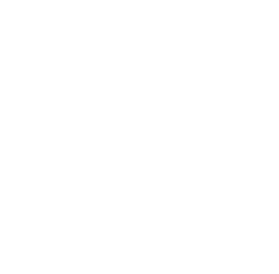
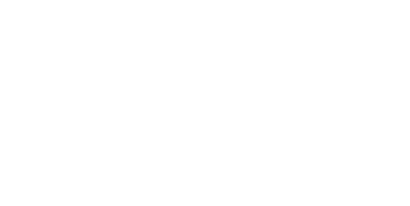
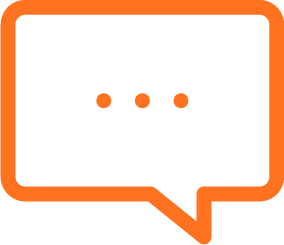


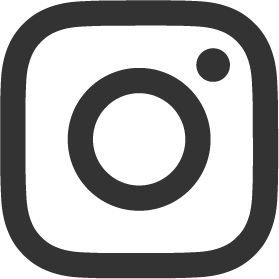
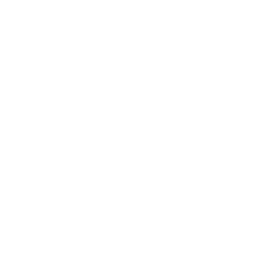
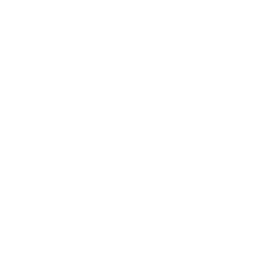
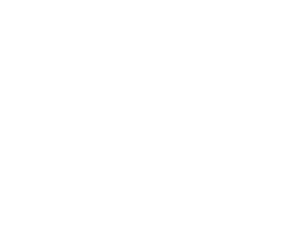 お問い合わせ
お問い合わせ
 アクセスマップ
アクセスマップ